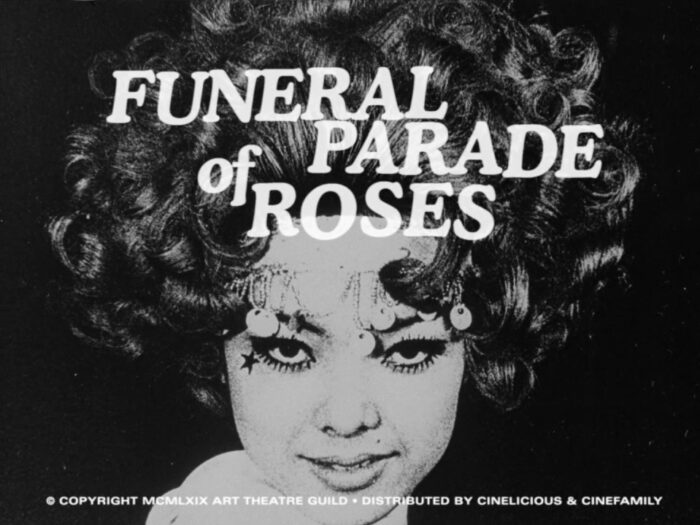
かつて銀座に有楽シネマという小屋があった。フランス映画社配給のBOWシリーズなどを観るため、よく訪れた。ここはATG(アート・シアター・ギルド)の封切館でもあった。ATGは川喜多かしこが起ち上げた独立系の映画会社で、良質な外国作品を配給し、国内の映画作家には、その主体性を100%尊重して、1,000万円の予算で制作してもらう、という趣旨で運営していた。なので、映画作家はここで野心を発揮することができた。中には失敗作もあったが、挑戦できたということに価値がある。大胆な失敗作を顧みることができるというのは、文化の懐が深いという証拠だ。今の映画は失敗できない。製作委員会方式で出資者のリスクヘッジが図られ、誰それが出て、こういう内容で、出資企業のタイアップも抜かりなく作品に盛り込めば、ある程度の回収も見込めるだろうし問題ないでしょう。そんなんばっかし。こういう映画は予告編も、毎度毎度同じフォーマットで作られる。判で押したようなものばっかしで観ていてウンザリする。何故このようなものが作られ続けるのでしょうか。それは、作り手が、観客なんぞバカだと見下しているからであります。映画が、人生を狂わせるほどに恐ろしいものだと認識していないからであります。
今回は、問題ない映画は作らなかったATGの諸作でも、とりわけ異様で果敢な一本、『薔薇の葬列』(1969)を紹介する。

主人公は街中で、ゼロ次元商会によるハプニング演劇に出会す。劇場を取り払うと演劇はどうなるか、という試みだ。寺山修司率いる天井桟敷は、杉並区一帯に劇団員を放ち、一般家庭、銭湯、区役所など方々へ訪問させ、予告もせず演劇を催した。他人の迷惑省みず、所構わず自己表現がなされていた時代。今観ると、ちょっと恥ずかしい。この頃、日本は思春期だったのかも。
『薔薇の葬列』は松本俊夫の監督作品で、ゲイの少年を主人公にしたオイディプス悲劇のパロディーである。実に落ち着きのない作品で、ドラマがシリアスに展開しているかと想うと急にコミカルになったり、「この役についてどう想う?」と、やにわに出演者へのインタビューが挿入されたりと虚実入り乱れ、逸脱を繰り返して観客がドラマに没入することを拒む。しかしこの手法によって、角度の異なるものの見方が作品の中で相対化され、60年代末のラディカルな世相をフィルムに封じ込めることに成功している。
湯浅譲二による音楽は、エレクトーン一台だけ? って感じで、ちょっと音像の構築が貧相だが、その音楽も含めて、本作は『時計じかけのオレンジ』(1971)に影響を与えたと言われている。

キャットファイトシーン。
予告編では「性倒錯の実体を抉る」などと惹句が躍っているが、それは本作の真意ではない。同性愛も近親相姦もゲイ文化も、単に面白がって集められた題材に過ぎない。本作を俎上に載せてジェンダー問題を解明しようなどという試みも無意味だ。SNSの時代に入り、個人の性的志向がどんどん詳らかにされており、人類の「性」の多様さ複雑ぶりが露呈し始めている。これは、精神的な性自認に限らない。解剖学的にも、これはどっちだろう、というような生殖器をもって生まれてくる子も時々いるようなので、どうも人類というのは、男と女の二極の間にも色々いるんだと認識を改めたほうがよさそうだ。とりあえず、多目的トイレだけはデフォルトで設備すべきだ。それは賢い旧人類の義務だ。
『薔薇の葬列』は、商業映画でもあり実験映画でもある。前衛と通俗との間に平然と架け渡された橋梁である。本作は、終始シュルレアリスムの手法で描かれている。そういえば、『ドグラ・マグラ』(1988)の公開時だったか、松本俊夫監督の実験映画の回顧展があった。三台の映写機を並列し、三つのイメージをコラージュさせる『つぶれかかった右眼のために』(1968)では、粉ミルクのコマーシャルフィルムと、ホルマリン漬けの奇形児が同時に映された。恣意的なイメージへの誘導が感じられる作品が多かったが、基本的に松本俊夫は、シュルレアリスムに籍を置く作家であろう。

シュルレアリスムは「超現実主義」とも訳されるので誤解されがちだが、この「超」は、現実を超えるという意味ではない。ニュアンスとしては、女子高生が「超可愛い」と言う際の「超」と同じである。強度の、過度の、という意味合いで、「替玉バリ硬」の「バリ」、『Yeah! めっちゃホリディ』の「めっちゃ」と同義である。おそらくロマン主義の「レアル(現実)」を受けて発展させた概念だと想われる。日常的な慣習や制度、効率化、経済化のために感覚が塞がれ、閉ざされた現実に対し、超現実とは、まだ世界と自己とが分離されてない幼い頃の現実。言語(概念)によって規制されない、生きた感覚の現実であり、同時に、人類のアカシックレコードのような現実でもある。それは別次元のものではなく、作法さえ心得ていれば実感できる、居住まいを改めるだけで起ち顕れてくる現実である。
.jpg)
けれどこのシュルレアリスム、どうも思想として未熟というか進化の過渡期にある気がする。アンドレ・ブルトンが熱っぽく宣言したような人間革命に発展することは、到底ないと想われるし、実際ほとんど理解されていない。その割に、「オモロいやんけこの絵え。なんか訳解らんけど、めっちゃシュールやん」と、そのアプローチには大衆の気を惹く通俗性がある。
シュルレアリスムの技法が最大限の力を発揮でき、この運動をさらに発展させる可能性を秘めた媒体が、映画である。映画は観客のイメージを規定し、誘導する。直接神経に働きかける。そうして現実と超現実とを連絡する通底器となる。
映画とシュルレアリスムとは、ダリとブニュエルが『アンダルシアの犬』(1929)を共作した頃から相性がよかった。超現実へにじり入るには傷口が必要なのだ。その傷口となるのが、アブジェクティブなイメージである。不安に駆られるようなイメージ、おぞましくも魅惑的なイメージである。映画は自在にイメージの刃を振るう。シュルレアリスムの作法を心得ている。異なる具象の並置により別のイメージを喚起させ、連想させ、異化させる。映画は遠慮なくやってしまう。だからできるのだろう。映画にはらわたがあるなら、アブジェクティブなイメージとエロティシズムが、そこに脈動しているはずだ。

おそらく、アブジェクティブなイメージは、言語に規制される前の現実に於いて、最も強烈なものだったはず。混沌とした無秩序の森では、陰からこちらを覗き込む目や鳴き声や揺れて踊る樹々や刺すような赤い西陽など、様々なイメージが一挙に押し寄せてくる。イメージの氾濫そのものが、人類の郷里の風景なのだ。オートマティスムやコラージュなどの手立てでその頃の感覚を取り戻そうとする。食み合い、歌う。朽ち果て、生まれる。混沌とした生命の明滅を、世界まるごと感じ取っているのだ。当然、まだ高度な言語を持たない心には処理し切れない。目の前の獣の死骸も、それと認識できない。獣はまだ生きているようだ。けれどもよく見ると、小さな虫が群れをなして、獣の体を食い荒らし始めている。獣は今にも動きだしそうに艶かしい。が、どんどん食い破られてもいる。ジョルジュ・バタイユが言う、死を予見することで発動するエロティシズム。そのような感覚が閃く。これが傷口となり、超現実への通用口となる。
個々の人間の一生はあまりにも短く、その身体も物理的に儚い。けれども我々は、選んだ覚えがないのに似通った姿形を引き継いでいるように、人類総体の記憶も引き継いでいる。普段の生活の中では、その記憶にコネクトできない(便宜上、我々自身がそうしている)。シュルレアリスムの作法によって、一時的に里帰りすることができるのだ。ただ、その郷里はあなたの全てを奪う、哀しい残忍な場所である。でありながら、最も活き活きと輝くものまで、間違いなくそこにあるのだ。そして優れた映画もまた、観客にとって、そのような郷里として存在している。
松本俊夫の作品には、暴力的なイメージや不気味なイメージなどで観客の気を惹こうとする俗っぽいところがある。それでもなお理路整然としており、シュルレアルな映画として方針に矛盾がないのは、先述した通り、シュルレアリスムそのものが通俗性を孕んでいるからだ。

『薔薇の葬列』では、まだゲイボーイになる前の主人公が、鬱屈した想いを抱えて鏡台の中の自分とキスを交すシーンがある。様々な想念を喚起させる場面だ。本作で最も重要なシーンかもしれない。
「人間に器官なき身体を作ってやるなら、人間をそのあらゆる自動性から解放して真の自由にもどしてやることになるだろう。そのとき人間は再び裏返しになって踊ることを覚えるだろう。まるで舞踏会の熱狂のようなもので、この裏とは人間の真の表となるだろう」アントナン・アルトー『神の裁きと決別するため』

『薔薇の葬列』は表と裏についての映画でもある。劇中では、男と女、表層と実相、虚構と現実といった、表裏二極の概念が提示される。物語が展開するにつれ、二極の概念は激しく揺さ振られていく。
ラスト、主人公がオイディプス悲劇を踏襲し、自らの目を潰して白昼の街路へ彷徨い出るシーン。それまで編集によって試みられたことがワンカットでなされる。ここでは、虚構と現実、表裏二極の隔てが溶解し、一元化している。本作を、既存の劇映画を想定してきた観客に映画を問い質す、ハプニング映画と呼んでもいい。このラストシーンが見事だ。『顔のない眼』(1960)のラストに勝るとも劣らないほど美しい場面だと想う。裏返って顕れたのだろうか、映画が剝き出しになった瞬間である。
